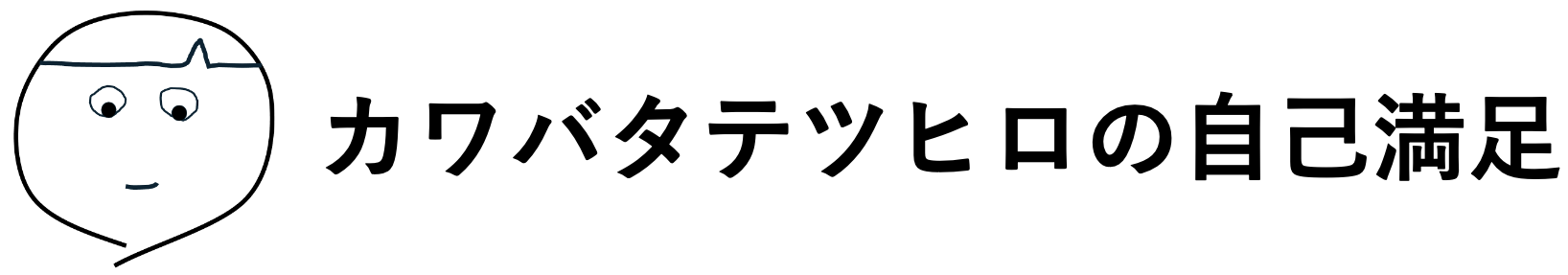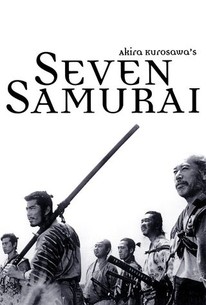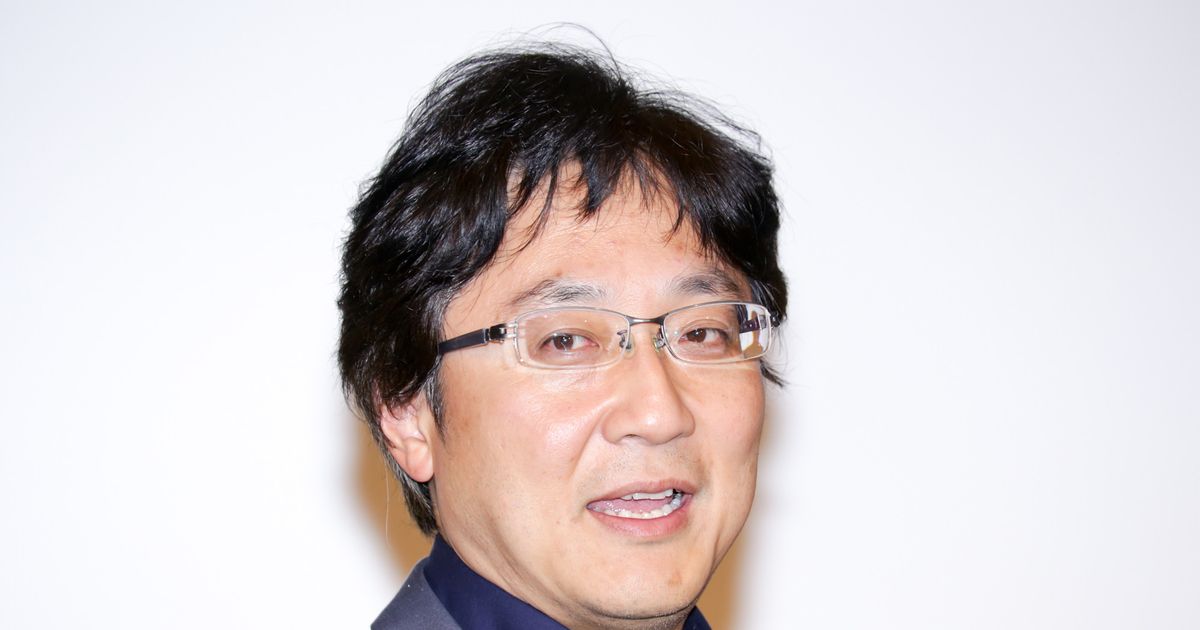日本映画の最高傑作だ!と言われることが多い「七人の侍」
今回、4Kリマスター版が期間限定上映されていたのでちょいと観に行くと、モノクロで、セリフは?で上映時間は長い、休憩(インターミッション)があるわで映画を観続けてきた中で経験したことがないことが大量大量大量。
まだまだ映画って奥深いものですねぇ。と某金曜ロードショー的の映画解説者みたいな気分になったんだよ。
目次
やっていたんです。傑作が
休日。久々の休日だ。自分としては休日になったなら、選択肢に「遠出」が浮かぶ。
もし金と時間が許すならば適当に行きたい場所まで飛行機でビュン!新幹線でビュン!と行きたい。ただ、残念なことに潤沢に使えるお金は銀行口座に無い。それどころか増えているのはクレジットカードの利用残高。休みもそこまであるわけじゃない。休日が終わった次の日はまたつまらない労働っちゅうものをヤラねばならぬのだ。
では、そんな休日をどう過ごすのか。次なる選択肢に浮かぶものは「映画鑑賞」になる。旅行と同じで大きなスクリーンに映し出される世界は自分を奮い立たせてくれるものばかりである。だから何度も呆れ返られても映画館へ足を運ぶのだ。
ただ、今回の休日は・・・ちょいと気が乗らない。それは何故か。
ここ最近観た映画だとチェンソーマンであるとか、ワン・バトル・アフター・アナザーであるとか、8番出口であるとか、国宝であるとか。
それらの作品は絶対に見逃すまい!と思い、映画館に足を運び、自分の目で観てきた。映画館に向かうことはどこか義務と感じている。
ただ、あまりにも新作を観るスパンが速すぎた。週に3回も映画館へ向かったこともある。そうなるととある問題が発生する。
それは「映画を観たいけど、観たい映画がない」という状態に陥ってしまうことである。それが今である。
もう殆ど観てしまった。残すはお子様向けの作品だったり、特定の思想を持った人々に打ち出しているドキュメンタリー映画ぐらいしか残っていない。こりゃまいった。
と思っていれば、映画サイトで上映作品の中に「七人の侍」を見つけた。

2025年。令和も気付けば7年が経過しているこの現代に「七人の侍」の文字。パソコンに向かっていた体はだらけきっていたが、思わず体を起こしてしまった。
なぜ再上映されているんだろう
今回の再上映は「午前十時の映画祭」によるものだ。
午前十時の映画祭とは全国の映画館で過去の名作を再上映する企画であり、Wikipediaによれば2010年から続いているそうだ。午前10時と書いてあるが映画館によっては11時に公開されたり、午後やレイトショーとして公開されることもたまにあるそうだ。
この企画では洋画・邦画を問わず名作が上映されており、2025年10月現在でこれから上映される作品には「アマデウス」「ウエスト・サイド物語」「シザーハンズ」「ニュー・シネマ・パラダイス」と名作が揃いすぎてとんでもねぇ状態になっている。
そして10月17日から11月6日までの約3週間に及ぶ期間で日本映画の歴史に残る、名作も名作な「七人の侍」が再上映される。ということになったのだ。
七人の侍とは
時は戦国時代のとある貧しい農村。農民たちは野盗と化した野武士たちの襲撃を恐れ、おののいていた。そこで村を守るために用心棒を雇うことを決意、食うに窮する七人の侍を探し出し、彼らとともに野武士に対抗すべく立ち上がる……。
映画.comより引用
監督は黒澤明。出演者には三船敏郎、志村喬などなど日本映画に名を残す俳優陣が出演している。
1954年に公開された作品ながら、現代においても日本を代表する作品として多くの映画ファンから評価され続けている。
国外の映画サイト「ロッテン・トマト」では映画評論家のレビューが100%、一般利用者からの評価も97%と、バグってませんか?と言いたくなるほどに文字通りバカ高い高評価の数字を遺している。
さて、この「七人の侍」だが、私は一度も観たことがなかった。
観に行くしかねぇ、けど・・・
黒澤明監督の名はもちろん知っているし、七人の侍も当然知っている。ただ、一度も観たことがなかった。今ではサブスクを利用すれば簡単に観られるような時代だ。
なぜ観ていなかったのだろうか?
単純に1954年公開のこの作品を観たい!と思うきっかけが無かったような気がする。現在はIMAXだ!4Kだ!と高画質で映画を見ることが出来るというのに、わざわざモノクロ映画を観たいか?と考えるとあまり気は乗らない。ただ、名作だからいつかは観なければ・・・という思いがずっと募っていた。
そんな中で湧いて出てきた再上映。そうなれば素晴らしいきっかけである。七人の侍の再上映に際して予告編が公開されていた。
これを観ずにして映画は語れない。だそうだ。なるほど・・・

行くしかねぇか!
そんな思いでインターネットでチケットの予約をしようとした。その時だ。上映時間に注目が行った。

上映時間は「11:35〜15:15」「18:50〜22:30」という表記だった。
うーん??
11時30分からなぜジャンプアップしておやつの時間である15時になっちまうんだい・・・?19時前に始まって22時30分・・・?帰宅ラッシュも終わっちまっているじゃねぇか・・・
そう。七人の侍の上映時間はバカ長いのである。本編は207分。3時間27分も同一作品が流れるのだ。クレヨンしんちゃんとかドラえもんの劇場版なら2本ぐらい平気に見れてしまう。アンパンマンなら3.5本ぐらい見れちゃう。
現代はタイムパフォーマンス、略してタイパが重要だと言われる時代である。ショート動画というコンテンツもあって、1分1秒が細かく重要に取り扱われるそんな時代にそぐわない上映時間だ。ただ1950年代の作品であっても3時間は長すぎやしねぇかい!?
私はパソコンの前で狼狽えた。一度は観たかった傑作の再上映である。観に行きたい気分ではある。しかし、集中して観れるかしら・・・うーん。
やっぱ行くしかねぇか!
ということで、七人の侍を観に行くことにした。今回は映画の内容はそこそこに、長時間に及ぶ上映で経験したことを中心に感想をまとめていこう。
観る
今回はシネマコンプレックス・MOVIXで観ることに。流石に3時間以上の上映。いつものポップコーンとドリンクでは事足りないはずだ。
ということで、ポップコーンをLサイズ、更には個人的ベスト・フライドポテトとも言えるMOVIXのフライドポテトを布陣に据えて、七人の侍に備えた。
上映時間は3時間超えという七人の侍。見に行った日は平日の11時。果たして観に来る人はどれだけ居るのだろうか?
スクリーン内に入ると各列に2人いるような状態。合計で20人程度というところか。その殆どが60代以上の人たちばかり。幼少期や青年期に観た人たちが再上映によって集結しているような印象を受けた。
11時35分に上映が開始。と思っているとなんと予告が流れる。3時間以上も本編があるというのに、しっかりと予告を流している・・・少しぐらい免除してくれたって良いじゃん!と思ってしまった。
今回は”新”4Kリマスター
太鼓の音がスクリーン内に響く。腹の中を揺さぶるような音楽。いよいよ名作・七人の侍が始まる。大きなスクリーンに、
七人の侍
というタイトルが出る。喰らえと言わんばかりに出てきたタイトルに目が離せない。
今回の七人の侍は「新」4Kリマスター版である。1950年代から何度も再上映がされてきた作品で、過去には音声の修復や映像を4Kにコンバートした4Kリマスターが行われてきたが、今回は更に高画質・高音質となったので「新」4Kリマスターということになっている。
ただ、この「新」4Kリマスターの恩恵はどう受けられるのだろうか?別に以前の4Kリマスターでも映像はキレイだろうし、映画館で観るにしてもそこまでの差は無いと思うんだが。
セリフ問題
七人の侍を見るうえで、とある感想をTwitterないしXで見かけた。それは出演している三船敏郎の音声が以前のリマスターより聞きやすくなっているというものだった。
以前は聞き取りづらかったの?この人の感想なんじゃないの?と思いつつ、Google大先生で「七人の侍 セリフ」と検索すると

みんな思っていたようだ。
大傑作の実写版「進撃の巨人」で脚本を担当したおなじみの町山智浩さんも嘆くほどで、以前より七人の侍でのセリフが聞き取れない問題があったそうだ。
では今回リマスターされたのは実際にセリフが聞き取れるかどうか?気になるところだ。
観ていくと、時々ではあるが「?」と思うセリフがいくつか存在する。特に序盤は耳が慣れていないので「?」となる部分が多い。
あれっ?さっきの百姓は何て言っていたんだ?と思っていると、続けざまに「?」「?」と聞き取りづらい・わからないセリフが重ねられる。まぁ何を言っているのか話の流れからして理解はできるけど、という感じだった。
そんな中で村の長老である「儀作」が登場。コイツぁ・・・聞き取りづらそうな風貌だぁ・・・と思っていたら、セリフが何の問題も無く聞き取れて、人は見てくれによらねぇなぁと思ったのであった。
作品全体のセリフ自体に言葉の訛りが入っているから聞き取りづらい部分もある。その後は主要人物が出てきたら、耳が慣れてきてなんとか聞き取れる。
しかし、三船敏郎が演じる「菊千代」が出てくると音割れが酷く「おっとぉ!?」とビックリするほどに聞き取れない。「なんて言った?」と思わず首を傾げそうになる。
現在のデジタルで収録できる時代と異なり、フィルムで且つマイク性能も現代とは段違いだったことを考えれば、セリフにノイズが入っている・音割れがあって聞き取れないのは致し方ないのかもしれない。
今回はリマスター版であり、これでもかなり音質は向上しているという評価だ。リマスターが施されていない状態で「七人の侍」を観ると、殆どのセリフが聞き取れないという人もいるそうだ。
そうなれば、このリマスターで半分以上も聞き取れていることは十分すぎる。と自分で自分を説得した。
インターミッション
七人の侍は前述の通り、上映時間が3時間を超える超大作だ。
それでもストーリーは非常に単純な構成になっていて、大きく3つに分かれている。
まず村を守ってくれる「侍を集める」そして「戦いの準備をする」2つが前半107分に詰め込まれている。
最初こそはあまり侍が見つからないが、意外と侍がポンポンと集まっていくので「なんか、なろう系というか異世界モノに通ずるものがあるなぁ・・・」と変な思考を巡らせた。
侍も集まって、いよいよ戦いの時・・・!というところで、スクリーンにどデカく、
休 憩
という文字。そして1分も経たない内にスクリーン内に照明が灯る。ゾロゾロとご高齢のみなさんが立ち上がり、外へ。私はというと、
おおぉぉぉお!休憩だ!
この文章だけでは「休憩にテンション上がるヤバいヤツ」に見えてしまうが、これは現代の映画ではあまり経験できない物事なのだ。
七人の侍ではあまりの長時間による上映のため前半107分を過ぎたところで「休憩」英語で言えば「インターミッション(Intermission)」が設定されている。時間にして5分である。
上映時間が3時間を超える作品ではフィルムの交換や長時間に及ぶ鑑賞に疲れた観客のために「休憩」が設定されることが多くあった。
例えば「2001年宇宙の旅」であったり、「ゴッドファーザー」にもあったり、邦画であれば「沈まぬ太陽」にも休憩がある。
ただ、観客側が長時間に及ぶ鑑賞に慣れてきたということや前編・後編のように2部を別々の時期に公開する方が利益を得られるということも相まって「休憩」が含まれた映画はとても少なくなっていった。
最近の作品であれば「オッペンハイマー」は180分にも及ぶが「休憩」はない。
2025年9月に上映された邦画「宝島」も191分だが「休憩」はない。
そういう点もあり「休憩」が出来ることをとても楽しみにしていた。しかし、「休憩」に入ったらなんかテンション上がる!と思ったがやることはほぼ一つ。トイレに行くことである。というかそれ以外にやることはあまりない。
それにしても不思議な感覚だった。まだエンディングを観ていないのに明るくなり、一度スクリーンを飛び出すこの感じ。違和感だらけだ。トイレに行った後は「なんかこのまま戻るのもなぁ」と思い、コンセッション(売店)へ出向きジュースを更にもう1つ注文し、座席に戻った。
あれっ・・・?長時間の映画に備えてポップコーンやポテトを買ったというのに、休憩に入ったから自然とジュースを買ってしまったな・・・
映画の「休憩」というのは観る側にすればかなり気持ちが楽になる仕組みだなぁ。と個人的には思った。3時間近くある上映時間で途中で「休憩」があると思えば、トイレへの心配もなくなる。更に次の時間に向けてリフレッシュ出来るし、ついでになんか買うかぁという気分になった。これって映画館からしてみれば「売上」に繋がりそうだけどなぁ・・・
「オッペンハイマー」や「シン・エヴァンゲリオン」とか、最近であれば「国宝」とか、それらが3時間近い上映時間で映画を楽しむというよりも「トイレは大丈夫だろうか?」という心配が強かった気がする。
3時間を超える作品には積極的に「休憩」を取り入れてほしい気持ちである。しかし、それが乱立すると今度は映画館が大変になってしまうだろう。うーん。なんとも一長一短な仕組みだ。
5分の「休憩」は個人的には十分すぎた。トイレもそこまで混雑していなかったからというのもあるだろうけども。スクリーン内はまるで映画なんて上映していなかったかのように静寂。
しかし、開演を告げるブザー的なのは全く無いまま、急に真っ暗になって後編が始まった。
映画館で観たほうが絶対に良い
後編が始まり、いよいよ戦いの時。七人の侍という作品を見るうえで一体何がそこまで評価されているのか。
それは観る人それぞれによってポイントは異なるだろうが、個人的には現代にも通用する「表現」をカメラに抑えられたことかなぁ。と思っている。
現代の映画では危険な撮影ではスタントを使うことやCGを使うのが当然だけども、馬からズルリと落馬するシーンとかも「おお、アブねぇ・・・」となぜか目が離せないシーンが多すぎる。
更に出演者一人ひとりの動きが当に村を守ろうとしていて、必死な感じがヒシヒシと伝わってきて、フィクションなのに真実味を感じられる、その感じが凄い。
あとは以外にもコミカルな部分もあって、ずっと緊張の糸が張り詰めているわけじゃないんだなと発見することも出来た。
これらは名匠の黒澤明監督の手腕が成すものであり、魅力でもある。
多分これらは映画を視聴できるサブスクの視聴では感じられなかったところだと思う。ただ普通の名作に留まっていたはず。いくら名作と言えど、3時間もあって家でゆったりと観ていると真剣には見れなかっただろうし、スマホを片手にボケェと観るだけだったに違いない。
手を伸ばそうにも、きっかけが無く観ることがなかった「七人の侍」
映画が織りなす魅力、時代を超えた真剣さ。そして「休憩」の重要性。それらを体験するには映画館でしか味わえない。